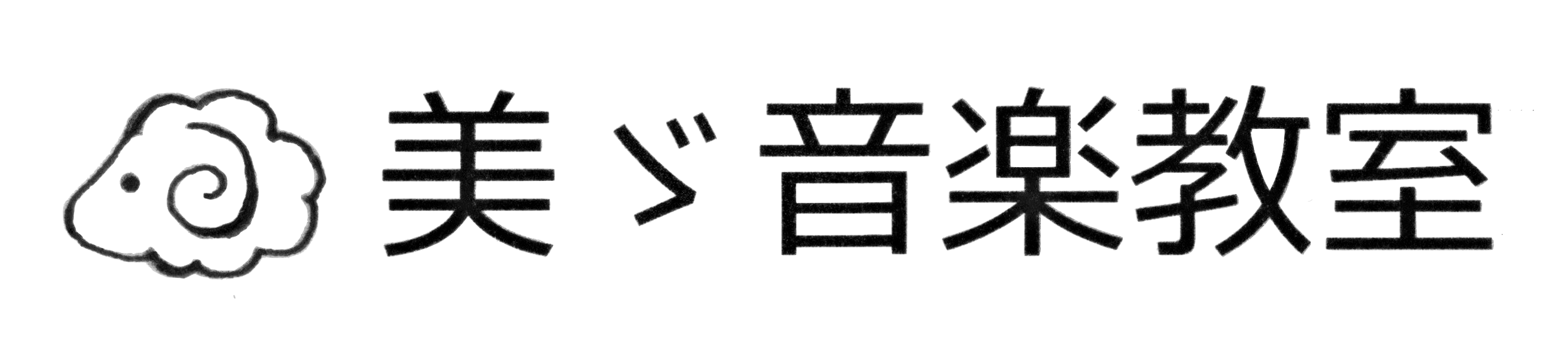ラフマニノフ作曲・ピアノ協奏曲第2番(分析)
ラフマニノフ作曲・ピアノ協奏曲第2番(分析)
ピアノを習ってみたいと思われている皆さんも、お馴染みの曲ではないでしょうか?
今日はラフマニノフ作曲のピアノ協奏曲第2番を分析しながらご紹介したいと思います。詳細に分析していくと、とても長くなってしまいますので、今日は第1楽章に絞って見ていきます。(少し難しい内容になりますが、なるべく分かりやすく書いていきます)
はじめに作品全体の概要です。
この曲はラフマニノフの作品としては初期〜中期の1900〜1901年に作曲されました。この作品は当時の協奏曲では一般的とされた3楽章形式で、編成は標準的な2菅編成(木管楽器が2人ずついる50名程度の編成)になっています。各楽章の配置や、楽器編成の点では、これといって特筆することはなさそうです。
では第1楽章を見てみましょう。第1楽章はハ短調で2/2拍子、ソナタ形式になっています。
さっそくスコアの1ページ目を開いてみます。ここはピアノの和音によるソロですが、触れておかなければならない点がいくつかあります。
まず一つ目は、第1小節目をハ短調のⅣ(ファ・♭ラ・ド)からスタートし、経過的に変化させながら、最終的にはプラガル終止(変終止)でⅠ(主和音=この場合はド・♭ミ・ソ)に持っていくことです。この形はラフマニノフの作品ではよく見られ、本作にも頻回に登場します。
次に第1小節目の和音の配置です。ここは左手に10度という、手が20cmは優に開かないと取れない音程が要求されています。20cm以上開くのはピアニストでも大変なことです。
和音を並べるとこういう配置になっています。
(右手)
ド
ラ♭
ファ
ド
(左手)
ラ♭(*)
ド
ファ
ここで仮に、一番省略できそうな左手の親指の音(*)を抜いてみましょう。すると音が一つなくなっただけなのに和音全体が随分軽くなって、あるいは寒々しく聞こえます。
この音は実は第3音といって、原型和音(ファ・♭ラ・ド)の真ん中の音にあたります。
一般的に第3音は重ねすぎると厚ぼったい響きになりますが、この効果が本作には悲壮感を表す際の「重さ」として必要だったと思われます。ラフマニノフは10度の音域が手の大きい人(ラフマニノフは手が非常に大きかったと言われています)しか届かないことは分かっていましたが、この響き優先し、止むに止まれず書いたと想像されます。
そこで手があまり大きくないピアニストは、これもまた止むに止まれずアルペジオで、つまりバラバラにして弾くことが習慣になっています。
もう一つ触れたいのは、5小節目です。この属7の和音を界に、両側4小節の和音が実は線対称になっています。属7和音は緊張感がありますが、どちらかというと明るい響きです。そして両側4小節は短3・減3和音が主体になった響きなので、ちょうど暗雲が続く中、一瞬光が見え、また暗雲に隠れるといったデザインになっています。
図で書くと、このような形になります。
「雲雲雲雲・晴・雲雲雲雲」
これは計画的にやらないと出来ないことで、実に凝った作曲法だと言えます。
2ページ目を見るとピアノは伴奏にまわり、オーケストラが旋律をとって入ってきます。11小節目、ここからが提示部です。
この部分で、オーケストラは1stヴァイオリン~ヴィオラまでを同度で重ね、集中した厚みのオーケストレーションで旋律を表します。これが第1主題です。一方、ピアノは間断なくこの旋律に身を捧げるようにアルペッジオを弾き続けます。アルペッジオでは、「ド・♭ミ・ソ」という構成音に対して、「♭ラとレ」のappoggiatura(い音)が付されているので、半音階的なぶつかりが増し、影を強めています。
第1主題の特徴は、その先頭を「ドーレ、ドーレ」と繰り返すところにあります。楽典の言葉で説明すると、「2度上行する動き」と言えます。これは重要な部分モティーフになりますので、今これをXとしましょう。またあとでXが出てきますので、覚えておいてください。
第1主題はこのXを起点にして、主として順次進行の動きを見せます。con passioneとあるので、情熱的にといった思いがあったようです。
第1主題の確保が終わった後、27小節目からチェロによるブリッジ(推移部)に入ります。このブリッジの特徴は、十分にこれもメロディックで主題的要素を持っている点です。また第1主題と同様に順次進行を主とした動きを見せる点、さらに先頭にXを持っていることが一番の特徴です。
このブリッジは少しずつ音域を上げていき、15小節間に渡る長いアナクルーズ(盛り上げ)を経て、42小節目でアクセント(頂点)を迎えます。そして12小節間の長いデジナンス(盛り下げ)が続きます。この間、ピアノは間断なくアルペジオを弾き、伴奏に徹底します。
55小節目でピアノがブリッジのメロディを受け継ぎ、Un poco più mossoとして経過的な楽句が挟まれたのち、Xを使い8小節間のアナクルーズ。その間にホ長調の同主短調Ⅳを借用した「♭ラ・♭ド・♭ミ」に持ち込み、79小節目で第2主題が提示されるホ長調に到達します。
ここも冒頭と同じようにプラガル終止によって新しい部分を導き出しています。
83小節目からが第2主題です。ここでやっとピアノがメロディをとります。この主題の特徴は先頭の3度、4度を含む跳躍進行にあり、第1主題の順次進行と対比させています。この跳躍進行も大切な要素なので、今これをYとしましょう。Yを含むピアノはオーケストラの背景に、さらに第2主題を確保し、経過的なパッセージを挟み、展開部に入ります。
展開部は、Moto precedenteの170小節目からです。
展開部で重要なのは、連打する動き「ソッソソソラファソ・ドッドドドッ」(展開部冒頭のバス:161〜163小節目)が加えられることです。この連打の動きも重要なので、今これをZとしましょう。
展開部では、第1主題に由来しているX(原型だけでなく、連続刺繍音や逸音を含む形や、拡大型や反行型に変奏されて扱われます)が主に使われますが、そのほかにYとZも随所に現れ、それらの要素がパズルのように組み合わされて音楽を形成しています。展開部は4部分に分けて見ることができます。
展開部の区分と、それを構成する要素を整理すると次のようになります。
- テンポ72のMoto precedente(161〜176小節目)=主にXとZが組み合わされて展開します
- テンポ76のPiù vivo(177〜192小節目)=主にXによる展開です
- テンポ80のPiù vivo(193〜224小節目)=前半がXとZの組み合わせによる展開、後半がYとZによる展開です
- テンポ96のAllegro(225〜244小節目)=ここはXと、3連符化したZによる展開になっています
そして、第1〜4部分の間に計画的にテンポを上げていき、第4部分後半でクライマックスを迎えます。
その後、クライマックスを持ち越すような形をとり、Maestoso(Alla marcia)の中で第1主題の再現をします。これは254小節目からで、ここからが再現部です。
このクライマックスを持ち越して再現部に入るやり方は特殊であり、なおかつ技巧的で、見事なまで再現部のバイタルを高めています。
ここではオーケストラが第1主題を、ピアノがZを受け持つ形でアンサンブルされているのも、これまた特徴的で、非常に趣向が凝らされた作曲法だと言えます。本楽章で、おそらく一番気合を入れたのはこの部分ではなかろうか、と想像されます。バイタリティと重厚感のある音像を表すことに成功しています。
その後、第2主題はホルンによって素朴に再現され、本楽章はハ短調のⅠで完全終止します。
本楽章のピアノとオーケストラの関係性は、提示部ではおおむねメロディ+伴奏という単純に区分けされた形が目立ちます。(第2主題が提示される際に一瞬ポリフォニックな美しい書法が現れますが)
それに対して、展開部と再現部では、提示部の諸要素を重ねることでピアノとオーケストラの関係が複雑なものとなっています。
いずれにしても、本作では高度な表現力が要求され、今日はご紹介できなかった第2楽章を中心にロマン派らしいピアニズムで語っていくので、多くのピアニストがレパートリーとし、演奏会でも人気のある曲となっているようです。
(宮川慎一郎)