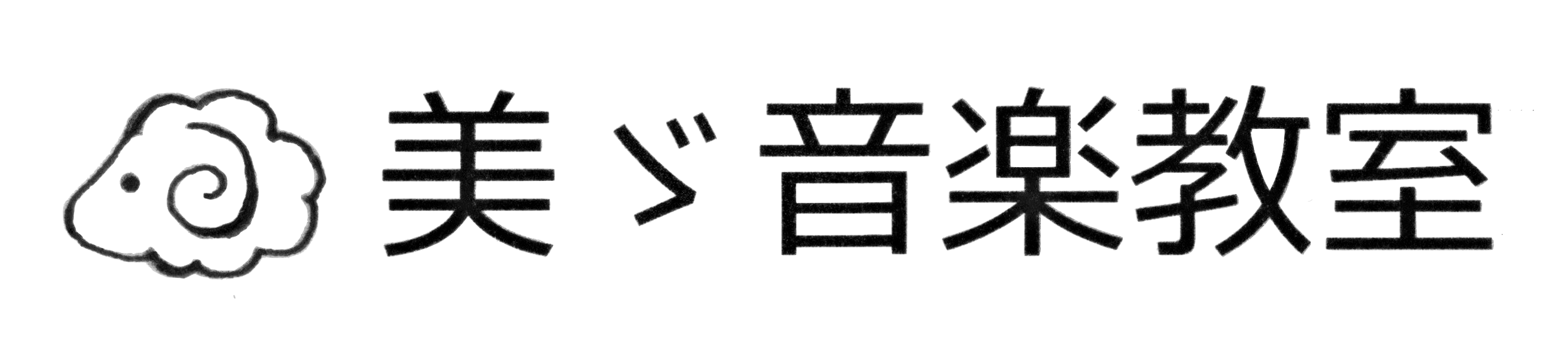バッハのシャコンヌ(分析)
ヨハン・セバスチャン・バッハには、パルティータと呼ばれるいくつかの曲があります。
パルティータはイタリア語のpartire=分割するからきていて、バロック時代では組曲という意味で用いられました。
パルティータは、当時の踊りをもとに定式化されたもので、およそ「アルマンド」「クーラント」「サラバンド」「ジーグ」という曲順で構成されます。またその中には舞曲的楽章と非舞曲的楽章が含まれ、個々は変奏組曲(組曲同士が変奏されたもの)としての関係を持っています。
バッハのパルティータは、ピアノやヴァイオリンのためのものが有名です。そのうち、シャコンヌを含むパルティータBWV.1004は、ヴァイオリンソロのためのもっとも重要な作品の一つといって良いと思います。
ヴァイオリンのための無伴奏パルティータ第2番 ニ短調BWV.1004は、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグという定式のあとに、シャコンヌが異様な長さで配置されています。
ところで、シャコンヌという題名は、題名というよりは曲種を表す言葉です。
シャコンヌは、同じバスの形を繰り返す中で、旋律を装飾的に変奏していく形式で、この手法をオスティナート技法と呼んでいます。
パルティータBWV.1004に含まれるシャコンヌは、カデンツを持った4小節単位のバスが繰り返されます。
これがニ短調の前半部分で32回変奏され、中間部の二長調では19回、後半部分では12回変奏されることで曲が成り立っています。
オスティナート技法ではバスが一貫して奏で続けられる場合もありますが、その一方で、バスがあるものと想定して変奏が行われていくことがあります。
バッハのシャコンヌの場合は、部分的にバスがあるものとして変奏が行われますが、各変奏は同じバスの上に乗っているとは思えないほど多様であり、バッハの作曲技法がいかに高度であったかと思わされます。またヴァイオリン奏法の上でも大変難易度の高い曲で、これがコンサートヴァイオリニストとしての一つの試金石となってるほどです。
そうは言うものの、実はロマン派の時代には、この作品をソロとして演奏することは不十分であると考えられていました。そこで、シューマンなど当時の作曲家がピアノ伴奏をつけ、演奏されていました。現在、それらのいくつかは楽譜が残っていて、シューマンとメンデルスゾーンのものが有名です。(両者のピアノ伴奏は、それぞれの性格をよく表しており、非常に対極的です。シューマンの方が繊細で私は好きです)
シャコンヌの構成要素は、和音体になっている部分と、旋律体になっている部分の二つに大きく分けられます。
このうち和音体では、全ての構成音をピアノのように補うことはできないので、主要な音(一度と三度)を除いた構成音が部分的に、あるいは全体的に省略されています。
一方の旋律体では、経過音や刺繍音などの非和声音を多用した変奏も多く見られる反面、和音体との中間体であるアルペジオの形をとったものもあります。
バッハのシャコンヌは、これだけの名曲なので、色々な楽器のための編曲があります。
有名なものはブゾーニのピアノ編曲のもので、これは豪華絢爛、ピアノのテクニックを余すところなく使った聴きごたえのあるものです。
また私の恩師である野平一郎もヴィオラ四重奏のために2回編曲しており、それぞれ指向の異なったものとなっています。
ちなみに私もシャコンヌは3回ほど編曲したことがあります。
最後に余談になりますが、編曲は厳格な様式(原曲の時代状況等を勘案した編曲法)に寄りすぎると編曲作業の途中で音が生気を失ってきますし、かといって自分の作曲スタイルに寄せすぎると編曲依頼者からクレームがくるものです。(お客さんはあくまでも原曲の雰囲気を聴きたいので)
とはいえ、依頼者も想定外のものが出来上がってくることに、内心ワクワクしているものでもあります。
(宮川慎一郎)