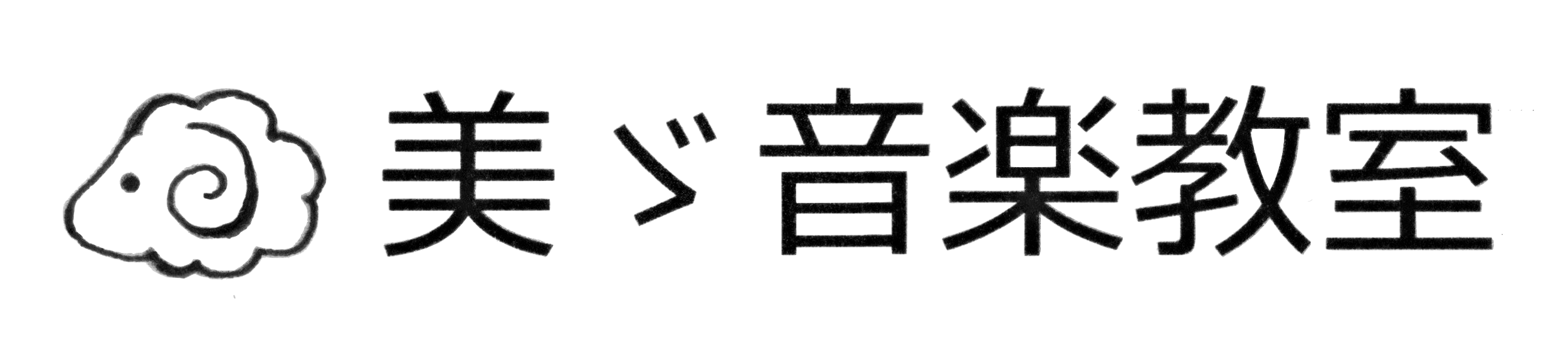ショパンのノクターン第2番(作曲法とピアノ演奏法)
今日はショパンの作曲法とピアノ演奏法についてお話ししていきます。素材として選んだ曲は、ノクターン第2番(Op.9 No,2)です。
この曲は非常に有名である反面、技術的に平易なため、ピアノ教室で大人のピアノレッスンを受け始めた方や、ピアノ初級者の間では、「弾いてみたい曲のベスト10」に入るのではないでしょうか。
さて、ではこの曲を弾くにあたって、ショパンがどのように作曲し、どのようなピアノ演奏を求めていたかを明らかにしていきましょう。
まずは作品の一般的な概要から。
作曲は1830〜1831年。マリー・プレイエル夫人(Marie Pleyel)に献呈されています。
変ホ長調、12/8拍子。
Andanteを主体としたテンポで、楽想としては、espressivoやdolceといった甘美なものを求めています。
形式は、
- A(1〜8小節目)
- B(9〜12小節目)
- A(13〜16小節目)
- B(17〜20小節目)
- A(21〜24小節目)
- C(25〜28小節目)
- C(29〜34小節目)
という小規模なロンド形式をとっています。またCはCodaとしての色合いが強いのが特徴と言えます。
では詳細に見ていきましょう。
- A(1〜8小節目)
冒頭は旋律をアウフタクトから導く、一般的な大楽節になっています。
1小節目の和声動向は、1拍目に主和音、2拍目に減7和音(同主調のⅦの借用)、3拍目に主和音と推移し、はじめ3拍間はミ音でバスを保続し、4拍目でレ音に経過的に下行させ、2小節目の1〜2拍でド音に着地させます。
着地点の和音はⅡ度調の属7和音で、続く3〜4拍目でⅡ度に解決します。ここの3拍目でも減7和音を一時的に用い、い音のように扱っています。
続く3小節目では、バスをシ音→シ(ナチュラル)音→ド音と順次進行する中で、和声はⅤ→Ⅵ調のⅤ→Ⅵと一拍ごとに推移し、4拍目でドッペルドミナントを置きます。
そして4小節目でⅠの第2転回形→属7→Ⅰ(主和音)という形で大終止を表します。
以上、4小節間に及ぶ和声的推移の中、6度および8度、そして10度の跳躍を特徴とする旋律が提示されます。ここまでが小楽節です。
次の4小節間の小楽節も和声的推移は全く同じです。そのため、左手はほぼ同じ伴奏形をとります。
一方、右手の旋律は変奏し、装飾的になります。装飾の主に刺繍音と、い音によって行われていますが、トリルを挟むなどピアノ独自の表現を用いているため聞き映えがします。
ピアノ演奏法に関して、冒頭の8小節間で気をつけなければならないのは、まず旋律の動向とそれに付随する強弱です。10度の跳躍の所に頂点を持って来る必要がありますから、それを念頭に前後のバランスを設定する必要があります。
次に、左手の考え方です。この左手はバスと内声を弾き分ける必要がありますので、バスからの内声の距離に応じて、また時には応じずに、テンポ感を作って行く必要もあります。
和声的推移は、できる限り、頭に入れておいてください。ピアノを演奏する上では何調の何度ということがわかる必要は必ずしもありませんが、バスが半音的進行をしていることや、その中でトニック・ドミナント・サブドミナントなどの役割していることくらいは少なくとも理解していることが必要です。
- B(9〜12小節目)
この部分の導入はEs durのⅤですが、主和音への解決を先送りしているため、属調に転調したかのようにも聞こえ、調性感は10小節目の3拍目までやや不明瞭です。
9小節目からのバスラインを追うと、シ(フラット)音→ラ(ナチュラル)音と半音ずつ下行し、10小節目でラ(フラット)音に到達します。この和声はEs durで分析するとⅤ→ドッペルドミナント→Ⅳとなっており、10小節目でⅣからⅠへ変終止をします。
11小節目では、B durのドッペルドミナント→属7→Ⅵとはっきりとした調性感のもと、Bの部分では最高音のシ(フラット)音からの流れがフォルテで表されます。その後、12小節目でⅡ→属7→ⅠでB durの完全終止をとります。
完全終止後は、バスを半音階的に下行させ、Es durのドッペルドミナント、属7まで持っていき、再現の準備をします。
Bの部分の旋律の特徴は、Aの部分と対比させる目的で順次進行を多用し、大きな跳躍を避けていることと、10小節目に表される同音連打(ミ音)です。Aに比べると、こぢんまりとした旋律ですが、多くの指示(強弱やテンポ、アーティキュレーション)が付されているため、印象深いものになっています。
Bの部分のピアノ演奏法においては、細かく記譜された強弱、テンポ、アーティキュレーションを注意深く聞くことがまず大切です。左手の奏法に関する注意はAの部分と同じですが、特にテンポに関して、バスの音型の上り下りを捉えながら進めることが大切です。
また音色設定に関して、Bの部分の冒頭は、Aの部分よりもやや素朴な印象で導入すると、その後のフォルテとB durへの解決が生きます。そして再現の準備部分は各響きをよく捉えることが大切です。この部分に限らず、この曲にはスラーの中にスタッカートが付いた箇所がありますが(スラースタッカートと言います)、これは滑らかな連なりの中で一音一音を区切って弾くといった奏法ですので、軽い音や、浅い音ではなく、しっかりと丁寧にタッチし、よく聞かせる音色作りをすると良いでしょう。
- A(13〜16小節目)
この部分は冒頭の小楽節(5〜8小節目)の変奏になります。左手は変わりませんが、右手はより細分化された装飾が施されています。
- B(17〜20小節目)
この部分も1回目のBの変奏です。やはり左手は変わりませんが、右手はやや装飾的になっています。
- A(21〜24小節目)
最後に表されるAです。2回目の変奏と然程変わりませんが、後半は終止感を強く出しています。
- C(25〜28小節目)とC(29〜34小節目)
この部分はコーダとも捉えられます。バスは主調の主音であるミ(フラット)音が支配的です。
特徴的なのは同主調(es moll)のⅣからⅠへの変終止を執拗に繰り返す点です。その中で、やがてトリルになって行く右手の2度の動きが変奏し、トリルなどを挟んだ後、短いカデンツァを置き、曲を閉じます。
- まとめ
さて、いかがだったでしょうか。
もうお気づきかと思いますが、この作品は、はじめのAとBさえ押さえてしまえば、ほとんど完成といって差し支えないものとなっています。
ロンド形式とは言っても、ごく単純な装飾が施された小ロンドと言ってよいでしょう。
しかし、この作品は冒頭8小節に大変大きな魅力があり、それがこの作品をここまで有名にしているのかもしれません。